先輩職員からのメッセージ(心理)
ここから本文です。
先輩職員からのメッセージ
埼玉県職員を希望する皆さんに対し、先輩職員からのメッセージです。

【心理】主事
福祉部 川越児童相談所 家族・自立支援担当
| 年月 | 所属 |
|---|---|
| 令和3年 4月採用 | 現課(所) |
現在の仕事の具体的な内容とやりがいを教えてください。
子どもの心理判定、心理面接やプレイセラピー、電話相談への対応などを行っています。
心理判定では、虐待や養育者の不在などによりこれからの生活の場を検討していく必要のある子どもに対して、その発達面の特徴や傷つきなどをアセスメントするため、さまざまな心理検査を実施します。家庭や施設にいる子どもに対しても、生活の中で見られる発達や行動上の問題について、児童相談所も一緒に対応を考えていくために判定することがあります。判定が終わったら、子どもが周囲により理解してもらいながら過ごせるよう、結果を説明します。
心理面接やプレイセラピーについては、主に施設で生活している子どもたちを担当しています。児童相談所に来てもらっているケースもありますが、施設を訪問して行うことが多いです。虐待の傷つきを遊びで表現する子ども、面接やワークを通して自分の感情に気づいていく子どもなど、見せてくれる表情はさまざまで、いつも子どもたちの柔軟性と潜在的なパワーに驚かされます。
難しさを感じることも多いですが、子どもが子どもらしく、のびのびと過ごしている様子を見聞きできることが一番のやりがいです。児童相談所では、それまでの過酷な経験の影響から、大人の顔色をうかがったり周囲に攻撃的になったりする子どもに多く出会います。子どもが持っている力を安心して発揮できるよう、日々考えることが自分の役目だと感じています。
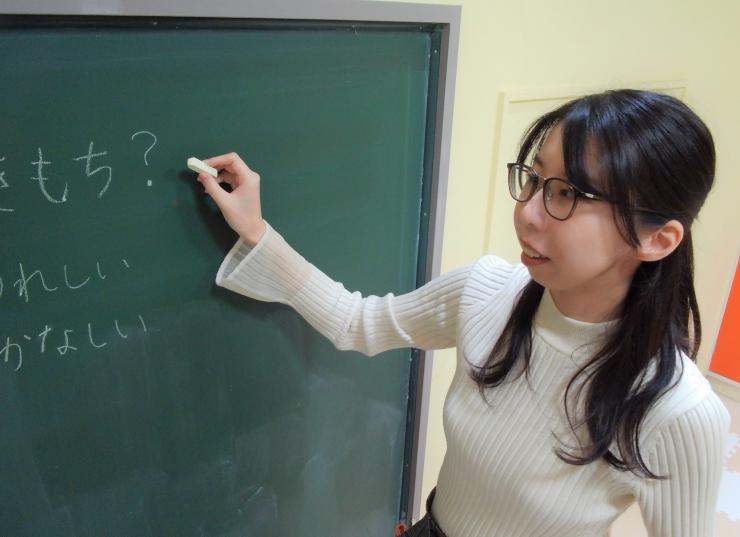
ある日の1日のタイムスケジュールについて教えてください。
| 時刻 | スケジュール |
|---|---|
|
9:20 9:30 10:00 12:00 13:00 16:00 17:00 18:30 |
出勤、1日のスケジュール確認 メールチェック、車で施設へ出張 施設職員との協議 昼休憩(外でランチ) 所に戻って記録作成、電話対応 プレイセラピー 記録作成、先輩職員に相談 退庁 |
※児童相談所は8:30~18:15開庁
※9:30~18:15勤務
職場の雰囲気を教えてください。
川越児童相談所には約80名の職員がおり、そのうち約20名が心理職です。心理職は子どもと一対一での関わりがほとんどですが、上司や心理グループの皆さん、福祉職の皆さんとチームで対応している感覚があります。互いに声をかけあって親子の見立てを共有し、家族にどのようなアプローチで関わっていくのがよいか検討していきます。
休憩時間には、いただいた旅行のお土産を開けながら感想を聞くなど、入庁前に想像していたよりも温かい雰囲気だなと感じました。
採用1年目の職員に対しては新規採用職員指導員(ブラザー・シスター)制度があり、ペアになった先輩職員から手厚いサポートを受けられます。私自身もたくさん教えていただいて、少しずつステップアップしていくのを実感しつつ、不安だった最初の1年を乗り越えることができました。心理職向けの所内研修もあり、先輩・後輩問わず学び続ける姿に刺激をもらっています。
今までの仕事で印象に残っていること、大変だったこと、うれしかったことについて教えてください。
暴力を受けて家を離れている子どもの心理判定で、検査に応じないどころか、名前すらも答えてもらえなかったときには大変戸惑いました。警戒心をあらわにし、答えまいと懸命に唇を引き結んでいる様子がとても印象的でした。上司からの助言で、それまでの私は“検査から言えること”に頼っていたのだと気づかされました。どうにか安心してほしいと思い、手紙やぬいぐるみを使った間接的なコミュニケーションを繰り返すうちに、遊びの中で怒りや傷つきを表現してくれるようになりました。警戒モードと安心モードについて心理教育をしたときには「○○さん(心理司)はいつもにこにこ、あーんしん」と言ってくれて、少しでも大人との間で安心して過ごせたのではないかと思うと、何よりもうれしかったです。このケースに限らず、子どもからもらった言葉を、自信をなくしそうなときのお守りにしています。
また、前年度まで担当していた療育手帳の判定業務では、子どもの知能検査を行ったり、保護者の方から生活状況を伺ったりしていました。どんなに慣れてきても、手帳に該当するかどうか、結果を伝えるときには毎度緊張していたように思います。子どもの特性に合わせた工夫を、日々接している保護者の方から学ぶことも多かったです。
埼玉県職員を志望した理由や、埼玉県職員になってよかったと思うことを教えてください。
他県出身ですが、これから自分のライフステージが変化していくことを考えたときに、自分もここに住みたい、ここで子育てしてみたいなどと思える自治体だと感じて志望しました。
実際に職員になってみると、心理職向けの研修が充実していて段階的に学べること、休みを取りやすい雰囲気があることなど、働きやすい職場だと感じています。産休・育休から復帰した先輩職員が、時短勤務やテレワークを活用しながら生き生きと働いている姿を見て、自分のキャリアプランもイメージしやすくなりました。別の児童相談所に配属になった同期とも、研修を通じてつながりができました。いつも相談に乗ってくれる同期の存在も、とても心強いです。
休日やプライベートな時間の過ごし方を教えてください。
退勤後や休日は家でゆっくり過ごすことが多いのですが、最近は絵の個展に行ったり、ふわふわした動物に触れたりして、五感を癒やしています。また、夏季休暇やリフレッシュ休暇を利用して、年に3回は実家に帰っています。現在の担当業務は自分で予定を決められることが多く、休みが取りやすいところも魅力の一つです。

これからの埼玉県の未来をつくる役割の一翼を担う県の職員として、今後チャレンジしたい事やどのような職員になりたいかを教えてください。
今後も心理に関する専門性を磨いていけるよう、勉強を続けます。例えば、児童相談所内でSVやコンサルテーションといった形で指導いただく機会があります。そういったものに積極的に参加して、先輩方から学び、子どもやその家族のニーズに合ったケアを提案・提供できるようになりたいです。
また、これまでを振り返ると、自分が職場で困っているときに温かく声をかけていただき、小さなことでも相談できていることが、結果として子どもへの対応にもプラスになっているように思います。子どもにとって安心でき、頼りがいのある職員になるために、同じ職場の方々にも安心感を持ってもらえるような職員を目指したいと思っています。
受験するにあたってのアドバイスがあれば教えてください。
受験した試験:職員採用上級試験(心理)
専門試験は幅広く出題されるため、それまで強い関心のなかった分野についても知識を固めるきっかけになりました。選択肢を見比べて、どの部分が選ばない根拠になるか、どう表現を変えたら正しい説明になるかなどを考えるようにしていました。
面接については、大学で開催されていた面接対策講座を利用してやりとりの練習をしていました。本番では緊張しましたが、考えてきた内容を上手に発表することよりも“伝えること”を意識して臨みました。
埼玉県を目指す方へメッセージをお願いします。
埼玉県職員、そして児童相談所の心理職について、興味を持っていただくきっかけになればと思います。皆さんと一緒に働ける日を楽しみにしています!